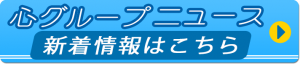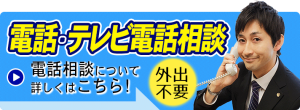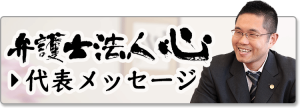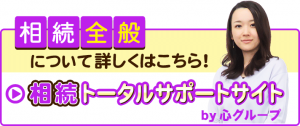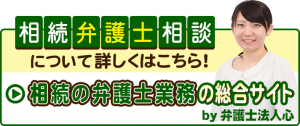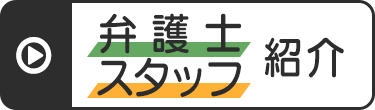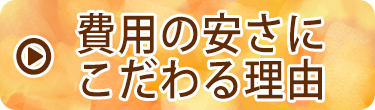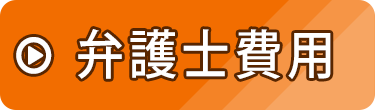生前に相続放棄をすることはできるか
1 相続放棄の原則
たとえば被相続人となる親が多額の借金を抱えていることが判明しているなどのケースでは、「生前に相続放棄しておきたい」とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。
相続放棄は「相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」にしなければならないと定められています。
「相続の開始」があり、これを「知った」というプロセスを経て、その時から「三箇月以内」というのが、相続放棄を行うことができるタイミングの要件です。
相続は、被相続人の死亡によって開始されます。
したがって、被相続人の死亡は、相続放棄を可能にする要件の1つとなります。
言い換えれば、被相続人の生前に相続放棄することはできないということになります。
2 混同されやすい遺留分放棄との関係
生前の相続放棄と混同されやすい制度として、遺留分の放棄という制度があります。
遺留分の放棄には、裁判所による許可が必要であり、許可要件も厳格ですが、生前に行うことができます。
ただし、相続放棄と遺留分の放棄とは、まったく別の制度です。
遺留分の放棄は被相続人の生前に行うことができますが、相続放棄は被相続人の生前に行うことはできません。
また、遺留分の放棄と相続放棄とでは、法的な効果もまったく異なりますので、注意が必要です。
3 生前から準備しておくことが大切
被相続人がまだご存命であっても、相続放棄をするべき財産状況であることが判明している場合には、事前に相続放棄の準備を進めておくことが大切です。
1に書いたとおり、相続放棄の手続きには期限が定められています。
そのため、生前から手続きの流れや必要書類について調べておくと、いざ相続放棄の申述をする際に、スムーズに手続きを進めることができます。
また、事前に、法定単純承認事由に該当する行為についての予備知識を調べておくことも大切です。
被相続人が亡くなった後は、被相続人が所有していた預貯金の使用や、動産・不動産の売却・廃棄、遺産分割協議等は、原則として行うことができません。
これらは法定単純承認事由に該当する行為となるため、行ってしまうと相続放棄が認められなくなる可能性が生じます。
被相続人が亡くなった後で、うっかり法定単純承認事由に該当する行為を行ってしまわないようにしておくことが大切です。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄のやり方
- 相続放棄をしたら裁判所から呼び出しを受けるか
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の必要書類について
- 相続放棄の手続きで必要な書類
- 相続放棄における財産調査でお悩みの方へ
- 被相続人の債務の調査方法
- 相続放棄はいつまでに手続きすればいいのか
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄をした際の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄をしたら、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄の効果とはどのようなものか
- 相続放棄ができないケース
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄の却下率とそのパターン
- 被相続人に関する金銭の請求について
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続人が相続放棄したかどうかを確認する方法
- 生前に相続放棄をすることはできるか
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄をした際に代襲相続は発生するか
- 相続財産の処分と相続放棄
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をする理由について
- 3か月が過ぎてからの相続放棄について
- 相続放棄の注意点
- 相続放棄と遺産分割協議との関係
- 被相続人と賃貸で同居していた場合の相続放棄
- 生活保護を受給している方の相続放棄
- 未成年の方の相続放棄
- 相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるのか
- 相続人全員が相続放棄した不動産はどうなるのか
- 相続放棄をする場合の香典の扱い
- 相続放棄と限定承認の違い
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒260-0045千葉県千葉市中央区
弁天1-15-3
リードシー千葉駅前ビル8F
(千葉弁護士会所属)
0120-41-2403